はじめに:会社でも社中でも「思い通りにならなさ」と付き合う
『結局、会社は思うように動かない』(著:下地寛也)という本を読んだ。
タイトルに頷きたくなる人も多いだろう。実際の内容もその期待を裏切らず、「会社」という一筋縄ではいかない生き物と、どう向き合っていくかについて、非常に実践的な視点で語られている。
著者はマネジメントもプレイヤーも経験済み。どちらの立場の言い分も理解したうえで、次のような行動指針を提案している。
- 会社の「アルゴリズム」を理解する
- 相手の思考パターンを読み解く
- 仕事の“ツボ”を押さえる
- 主体的にコミュニケーションをとる
とても端的で現場感がある。
この本を読みながら、僕は自然と茶の湯の世界に思いを馳せていた。企業での経験も、社中での学びも、根っこのところは案外似ている。いや、むしろ「人が組織となり何かを行う」というのは、多かれ少なかれそういうものなのだと思う。
この記事はプロモーションを含みます
「わかってくれない」は、やめる
本書が説くのは、「他人は変えられないけど、自分は変えられる」というシンプルな前提である。
プレイヤーとマネージャー、会社と個人——立場が違えば、当然優先したいことも価値観も違う。
だからこそ、
「なんでわかってくれないんだ」
という思いは、一旦横に置く。
その代わり、自分の考えを丁寧に伝え、相手の立場にも耳を傾ける。自ら働きかけて、関係を築いていく。
これは、職場に限らず、茶の湯の世界でも同じだと僕は思う。
社中という、もうひとつの「会社」
茶道の社中も、いわゆる組織みたいなものだ。
先生はCEOのような存在で、先輩方は上司。
「長くやっている人ほど上手い」という不文律があり、型や順序を守ることが大切にされる。
だからこそ、自分なりの主体性を持っていても、そのままでは空回りすることがある。
たとえば、あるお稽古の日。
先生「今日は何のお点前をやりたい?」
僕「濃茶の◯◯をやってみたいです(以前、先生が“次はそのお稽古をやろうね”と言っていたもの)」
先生「初めてやるものは、私から“やっていい”って言ったやつじゃないとダメよ」
僕「……はい(えっ、前にやっていいって言ってたジャン」
先生の性格にもよるし、一概には言えないけれど、やっぱり主導権は自分より立場が上の人にある。
だからこちらも、相手の「気分」や「間合い」に配慮しながら発言を選ぶことにならざるを得ないのが現実だ。
空気を読むことと、自分をなくすこと
僕は比較的、年配の方とも自然に会話ができる方だと思う。
しかしそれは、相手の発言に上手く合わせたり、基本的に「Yes」で返すようにしているからで、積極的に意見を出しているわけではない。むしろ、自分の意思はどこかで抑えている。
場の調和を守るために、自分の声をひそめる。
これは多くの場で起こることだけど、それが続けば、どこかに窮屈さを抱えるようにもなる。
それでも、コミュニケーションをあきらめない
人と分かりあうというのは、本当に難しい。
相手には相手の立場があり、価値観があり、これまでの経験がある。こちらがどれだけ言葉を尽くしても、なかなか通じないことはあるし、時にはそれが衝突につながってしまうことだってある。
正直なところ、僕自身はそうした対立や不協和を前にして、コミュニケーションを諦めてしまったことが何度もある。話さなければ、波風は立たない。ぶつからなければ、平穏は保てる。そんなふうに信じて、沈黙の中に自分の心の静けさを見出してきた。
しかし、その静けさは、本当の意味での平穏だったのだろうか?
コミュニケーションを断つことで、自分を守ったように思えても、実は世界との接点をひとつ閉じてしまっている。その分、自分の可能性や、本当に実現したいことからも、少しずつ遠ざかっていく。閉じられたコンフォートゾーンの中に留まることは、ある意味で「楽」だけれど、そのままで変化は起こらない。
コミュニケーションは、面倒だし、ストレスがかかるもの。
その前提を持ったうえで、なお続けていくという姿勢が、やっぱり大事なのだと思う。少しでも相手を理解しようとすること、自分の気持ちを小さくでも伝えていくこと。うまくいかなくても、やめないこと。そういう小さな積み重ねが、やがて大きな変化のきっかけになっていくのかもしれない。
コントロールできる世界を持つ
コミュニケーションを続けることの大切さを感じつつも、最終的には他人や組織を思い通りに動かすことはできない。どれだけ誠実に向き合っても、価値観が交わらないことはあるし、自分の想いが受け入れられないことだってある。それは、茶道の世界でも、会社でも、同じだ。
だからこそ、「自分がコントロールできる世界」を持っておくことが大事だと感じている。
たとえば茶道の稽古では、先生の指導のもと、与えられた流れに従って学んでいく。そこには順番もあれば、許可のプロセスもある。自分が「やりたい」と思っても、今はそのときではないと諭されることもある。社中という「組織」の中では、どうしても主導権は自分にはない。
でも、茶道は決してそれだけではない。自分で稽古の場を作ることもできるし、お点前を人に伝えることもできる。誰かの許可を待たなくても、お茶を点てることはできるし、茶会をひらくこともできる。必要なのは、ほんの少しの勇気と準備だけだ。
「自分の世界」を持つことは、逃げではない。むしろ、組織に依存しすぎず、自分の軸を保つためにこそ必要なことだ。そこには責任もともなうが、自由もある。そして何より、自分の力で一歩を踏み出せるという感覚は、何よりの原動力になる。
それは、自分の手で自分の道を切り開いていくということだ。
結局は、自分がどう在るか
会社でも、社中でも、家庭でも。
どこに属していても、相手を変えることはできない。
でも、自分のスタンスは変えられる。
- 組織の特性を知る
- 相手の背景や考え方を想像する
- 小さな行動から、自分の領域を広げていく
そんな風に、自分なりの余白を少しずつ作っていけたら、きっとどこにいても息がしやすくなる。
たくさんのコミュニティを持つことの有意性はそういうところにもある。
おわりに:湯のごとく、柔らかく
本書を読んでいて、組織とどう付き合うかの知恵を得るだけでなく、自分自身の姿勢を見つめ直す時間にもなった。
そして思う。
会社は思うように動かない。
社中もまた、思うようにはいかない。
でも、自分の姿勢しだいで、見える景色は少しずつ変わっていく。
社中という組織の特性を理解して、先生の特性を理解して、そして自分の道は自分で切り開く思考や気概を持つ。
その先にこそ、自分だけの「道」があるのかもしれない。
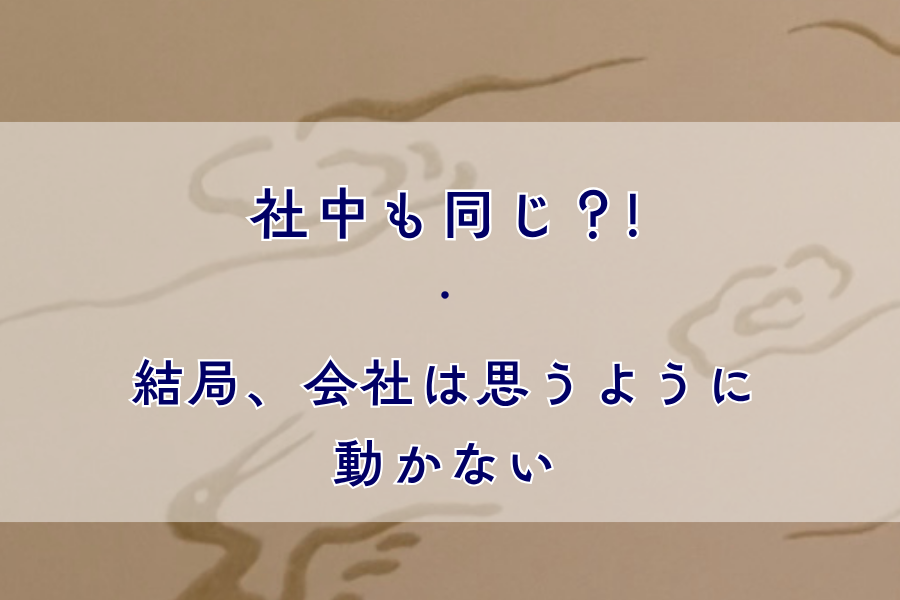
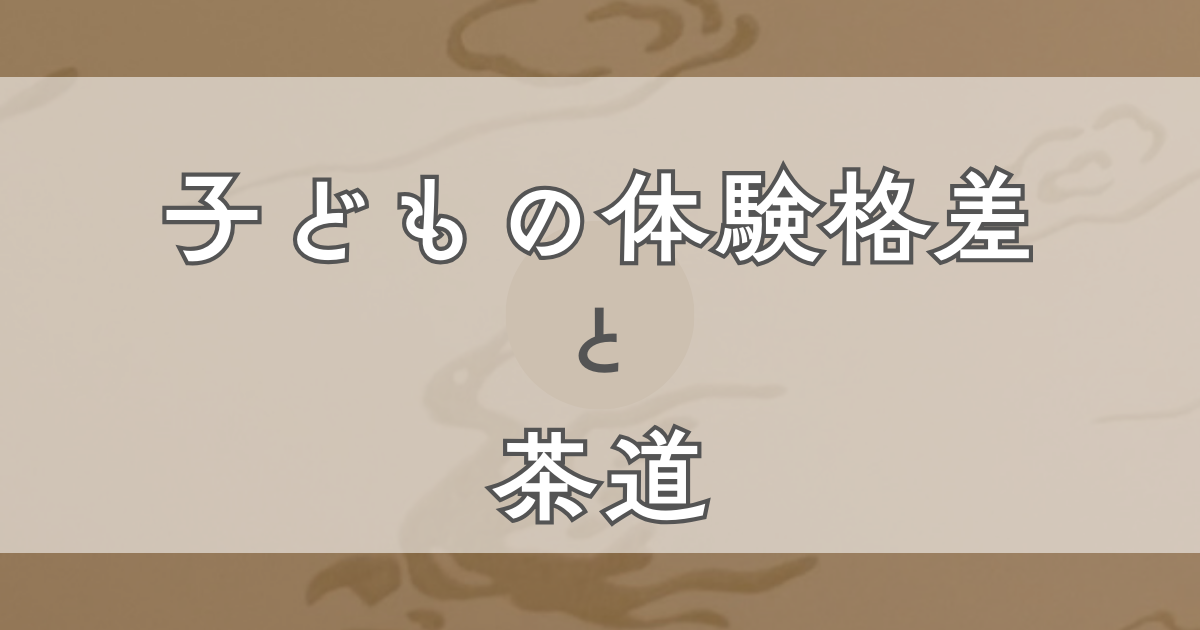
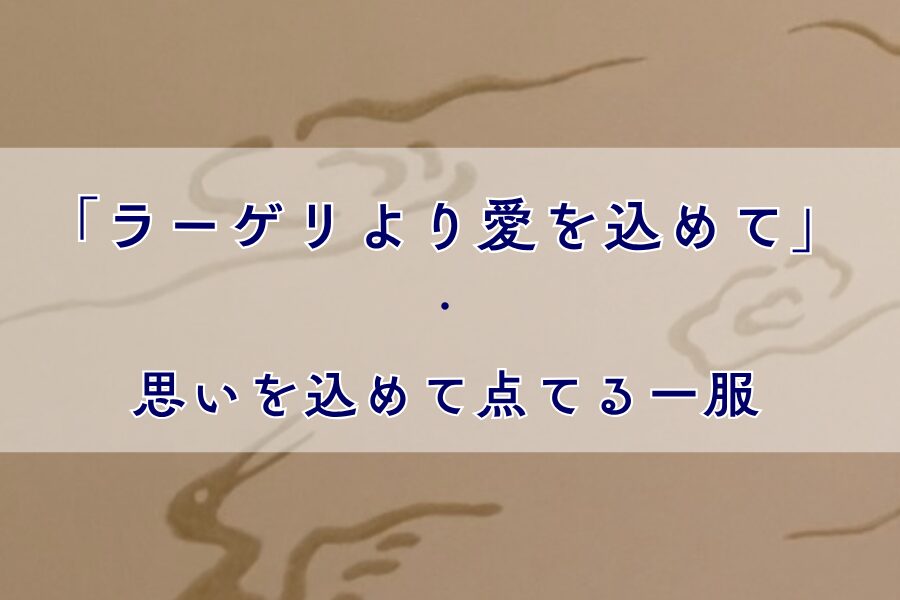
コメント