『子どもの体験 学びと格差(著:おおたとしまさ)』を読んで
最近、一冊の本を読みました。
タイトルは『子どもの体験 学びと格差』。
その名の通り、子どもたちが置かれている「体験の機会の格差」に焦点を当てた本です。
誰もが実体験として「体験がもたらす影響」を肌で感じているはず。
そんな中で、僕にとっては茶道が大きな影響を自分にもたらしたと言っても過言でありません!
この記事では、茶道がどんな体験をもたらすのかがわかります。
この記事はプロモーションを含みます。
「整えすぎた体験」が生む不自由

この本の内容の一部ですが、印象的だったのは、こんな指摘です。
「最近の子どもたちは、“大人が用意した体験”ばかりしている」と。
一見、それは良いことのようにも思えます。
安全で、効率的で、よく設計された体験。
でも、それが行き過ぎると、子どもが自分で考えたり感じたりする余白が失われてしまう。
自由な学びのはずが、決められたレールの上をただなぞるだけのものになってしまう。
そんなことを指摘していました。
茶道にあった“余白のある学び”
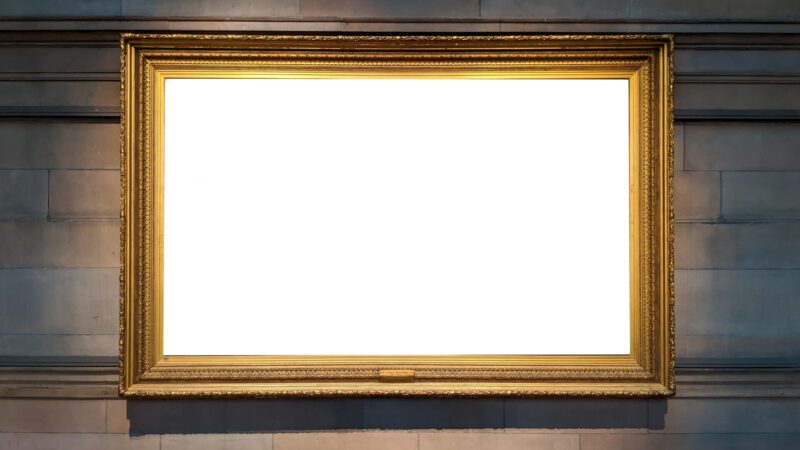
この指摘を読んで、ふと、茶道のことを思い出しました。
僕が茶道を習い始めた頃、いや今でもいろんな所作や点前順序を教わります。
でも、先生がその意味を詳しく説明してくれることは、あまりありませんでした。
「なぜ帛紗をこう畳むのか?」「この手順に意味はあるのか?」
そんな問いに、答えはなく、「そういうもの」としてひとまず受け取めていました。
とはいえ、『意味』や『目的』を重視するビジネスマンにとっては、その教え方に悶々とするでしょう。
(実際に僕もそうでした)
だけどそれは、今思えば、とても豊かな学び方でした。
意味が決まっていないからこそ、自分で「なんでだろう?」と考えることができる。そこに、自分なりの発見や納得が生まれていたのです。
感じることから始まる学び
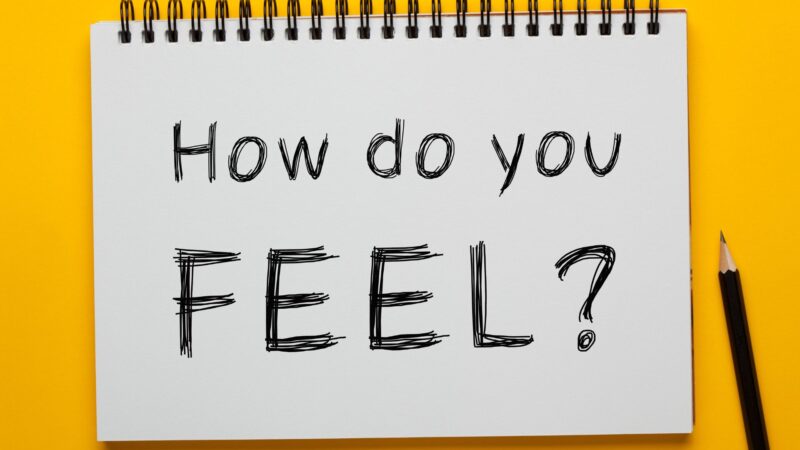
これは、いま子どもたちに必要な体験と通じるものがあるように思います。
与えすぎず、教えすぎず、整えすぎず。
ただそこに「場」を用意し、子ども自身が感じ、気づいていく時間を大切にすること。
茶道の稽古場には、そうした“感じる余白”が確かにあります。
子どもに渡したい体験とは

茶道を通じて教わったことの中には、「自然とともに生きること」「他者と調和して生きること」があると実感しています。
これもまた、茶道の根っこにあるものです。
季節の移ろいを感じるしつらえ、客人を思う道具選び、静けさの中の気遣い。
どれも、「学ぶ」のではなく「感じる」ことが入口になっています。
子どもには、そんな体験をしてほしい。
誰かに「良かれと思って」与えられたものではなく、自分の感性で育てていくような、自由で奥深い体験を。
茶道の場からできること

茶道に触れながら、そうした体験を子どもたちに、いや大人も含めてみんなに届けられたら。
整いすぎた体験から少し距離をとって、自由に感じ、考え、育つ時間を。
そんな願いを込めつつ、これからも人々が茶道に触れる機会を作っていきます。
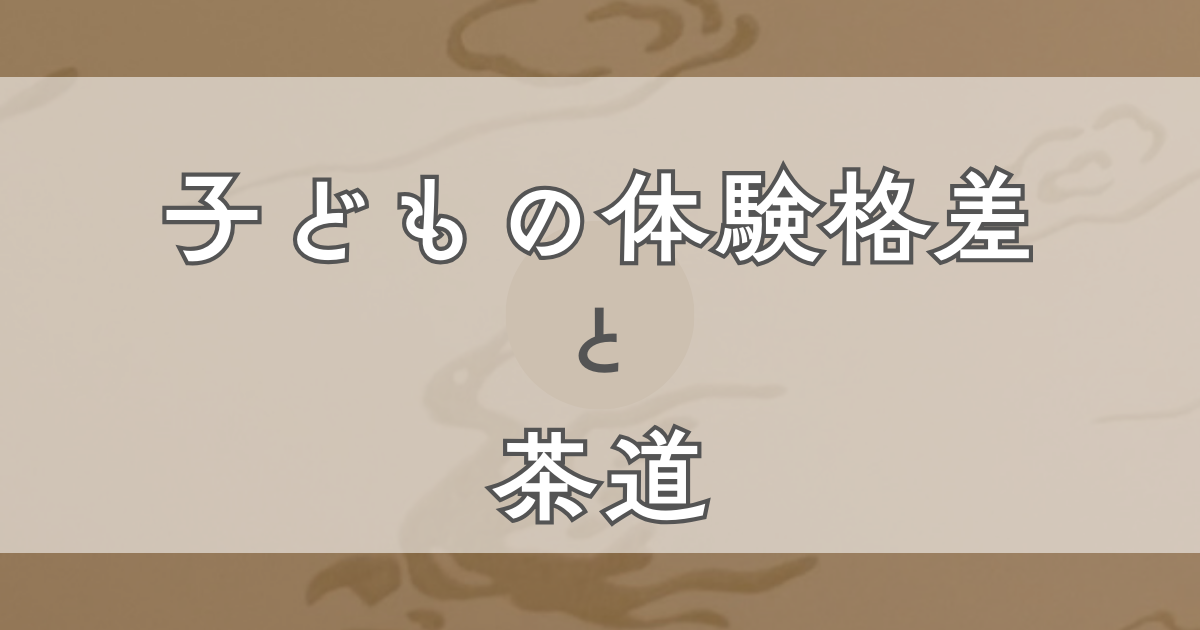
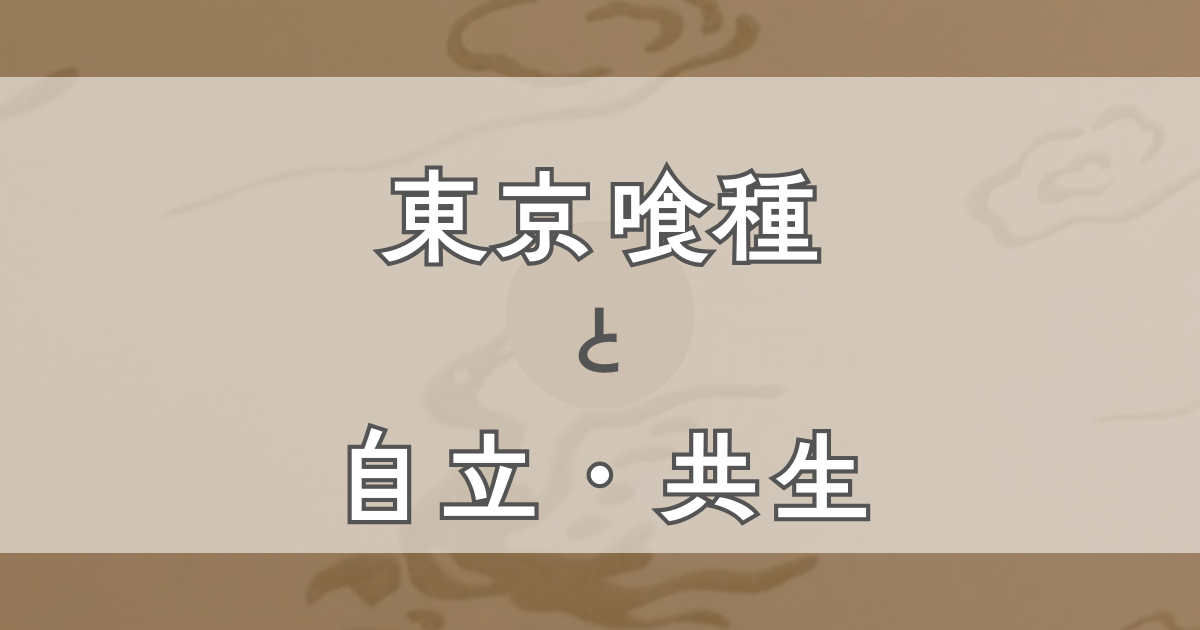
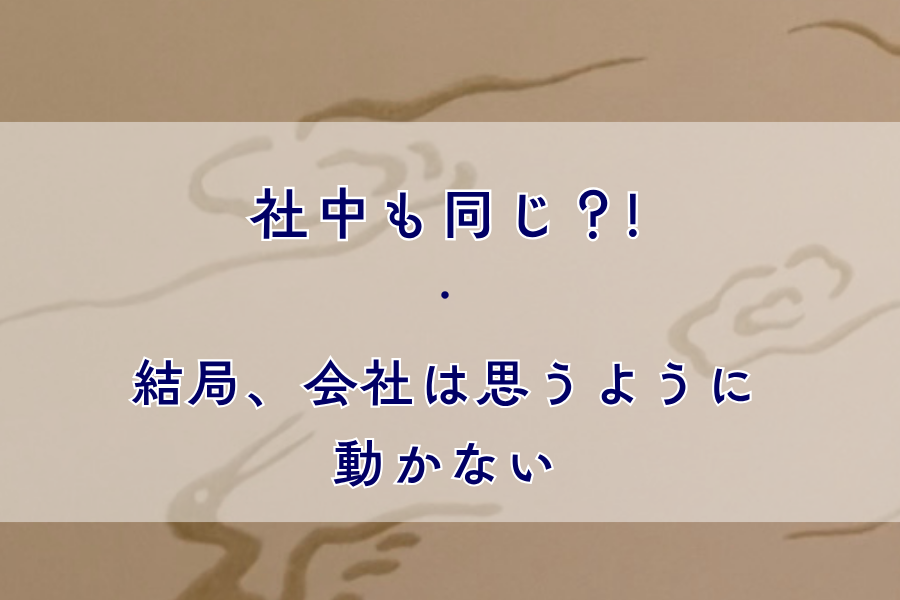
コメント